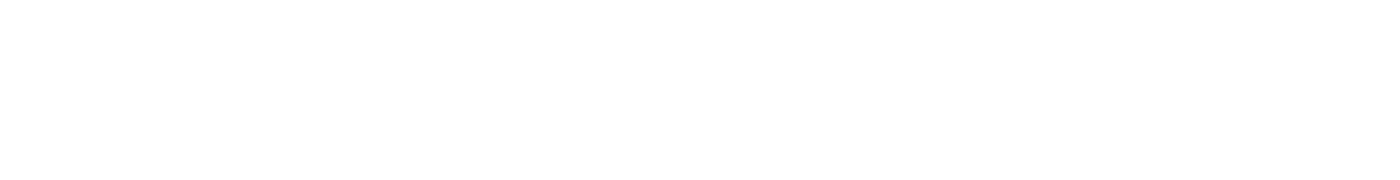第10回 認知症の親の財産手続き、どうしたらいい?―行政書士・FPが寄り添う相続・成年後見サポート
◆導入(悩みの提示)
「親が認知症になり、預金の解約や不動産の手続きが進められなくて困っています。子どもは3人いるのですが、誰がどう動けばいいのか分からないんです…。」
これは実際に寄せられたご相談の一例です。認知症を発症すると、本人が判断・署名できないため通常の手続きが止まってしまう ケースは少なくありません。財産の管理や将来の相続をどう進めるか、家族にとって大きな不安となります。
◆解決策(行政書士・FPとしてできること)
こうした場合に大切なのは、
・今すぐに必要な手続き(預金や不動産の管理)
・将来の相続に備える準備(遺産分割協議や相続登記)を切り分けて整理することです。
行政書士としての支援
・相続人の調査、戸籍収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成
・成年後見制度の申立てに必要な書類作成サポート
・コスモス成年後見サポートセンター(全国の行政書士が会員となる公益社団法人)の活用案内
FP(ファイナンシャル・プランナー)としての支援
・認知症後の介護費用や生活費を踏まえたライフプラン設計
・相続後の資産分配を踏まえた資金計画
・家族全体の将来の負担を軽減する資産管理のアドバイス
◆成年後見制度の選択肢
成年後見制度には大きく分けて「家庭裁判所への申立て」が必要です。
・ご家族が申立て人となるケース
・専門職(弁護士・司法書士・行政書士等)が後見人として選ばれるケース
・ご家族の事情により申立てが難しい場合、市町村長による申立て が可能なケースもあります
行政書士は、申立てに必要な書類の準備や流れのご案内を行い、スムーズな手続を支援できます。また、コスモス成年後見センター に登録している行政書士であれば、家庭裁判所から成年後見人に選任されることもあり、安心して任せられる体制があります。
◆結果(安心感)
今回のご相談では、
・相続人3人で話し合いの場を持つこと
・成年後見制度の申立ての可能性を視野に入れること
・将来の相続登記を行政書士がサポートできること
を整理し、具体的な行動のステップを描くことができました。
ご相談者は「制度や流れが分かったことで、兄弟で冷静に準備を進められる気持ちになりました」と安心されたご様子でした。
◆まとめ
認知症がある場合、本人の意思での手続きは難しくなります。だからこそ、
・成年後見制度の活用(家庭裁判所申立て、市町村長申立て)
・行政書士による相続・書類作成支援
・FPによる資産・生活設計の見直しを組み合わせて考えることが大切です。
ご家族だけで抱え込まず、専門家の力を借りることで道筋が見えてきます。同じような不安を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
暮らしの手続きアドバイザー、FP行政書士 瀬崎でした。
2025年10月6日