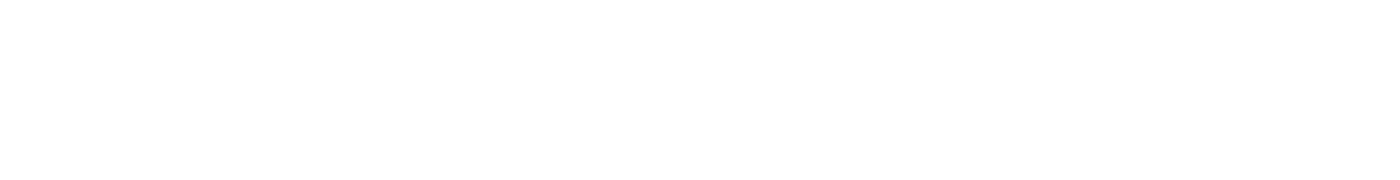第4回:行政書士・FPが教える「山の未来」の守り方
はじめに:実家に“山”がある方、こんなお悩みありませんか?
• 「実家に山林があるけど、何十年も誰も見に行っていない…」
• 「親が亡くなったけど、山の名義変更って必要?」
• 「草が生えてるだけの土地、税金だけ払ってる…」
• 「山を活用できないか、誰かに任せたい…」
こうした声を、私たち行政書士やFP(ファイナンシャル・プランナー)は多く聞いてきました。山林は、放っておくと「所有者不明土地」になったり、次世代にトラブルを残してしまうこともあります。今回は、「山林の相続・名義変更」「経営委託のしくみ」「注意点や活用法」について、最新制度も交えてわかりやすく解説します。
【事例紹介】「父の山」をそのままにしていたAさんのケース
鹿児島県I市在住のAさん(50代男性)のケースをご紹介します。
「10年前に父が亡くなって、相続の手続きをしたつもりだったんですが、山の登記は放置していました。ある日、市役所から『森林経営意向調査』という書類が届いて…。その山の所有者が“亡くなった父名義のまま”だったんです。」結果、登記を怠ったことで相続人全員の印鑑証明や住民票を集めることになり、手間も費用もかかることに。
なぜ“山の手続き”が大事なのか?
相続登記が義務化されました(令和6年4月~)
これまで任意だった相続登記が、2024年4月から義務化されました。
• 相続を知った日から3年以内に登記しないと「過料」も
• 所有者不明土地や放置された山林の増加に歯止めをかける制度改正です
📌 出典:法務省「相続登記の申請義務化」▶リンクはこちら
放置山林が災害や資産トラブルの原因に
• 倒木や土砂崩れの原因になった場合、所有者の責任が問われる可能性も
• 他人に売る・貸す・信託することも、名義が自分でないとできません
「森林経営管理制度」で“山を任せる”ことができます
2019年から、自治体が仲介して山の管理を委託できる制度が始まっています。
制度の流れ(ざっくり)
1. 自治体が所有者に「管理する?任せる?」と確認(意向調査)
2. 管理を希望しない場合 → 市町村が林業者などに委託
3. 山の整備・間伐・活用をプロにおまかせできる!
ただし…
🌲相続登記をしていない山林は、この制度の対象になりません。
行政書士のサポート内容
行政書士は、次のようなサポートを提供できます:
• 山林の名義変更(相続登記)に必要な戸籍や図面の調査
• 相続関係説明図や委任状の作成
• 森林経営委託に必要な契約書や申出書の作成(行政書士は申請書類の作成までを行います。)
• 所有者不明森林のための手続(民事信託・共有分割など)の提案
FP(ファイナンシャル・プランナー)のサポート内容
山林は「相続税評価」「納税」「活用」にも関係します。
• 固定資産税や相続税のシミュレーション
• 山林を売却・信託する際の注意点
• 補助金や税控除制度の説明(例:林業経営者への貸付による優遇税制)
• 「山を持ち続けるべきか」の判断材料を提供
【まとめ】山林も、未来への“資産”です
山林は、「価値がない」と思われがちですが、正しく管理すれば資産になります。
• 放置して罰則や責任リスクが出る前に、まずは登記を済ませる
• 自治体や専門家と連携し、「山を活かす」選択肢を考える
• 使わない山は、売る・貸す・信託するなどの整理も視野に
参考文献(2024年~2025年)
資料名 概要
法務省「相続登記の申請義務化について」(2024年) ▶リンクはこちら
林野庁「森林・林業白書 令和5年度版」(2024年6月公開) ▶リンクはこちら
参議院調査室「森林経営管理制度の課題と展望」(2025年4月) ▶リンクはこちら
📞 ご相談ください!
「山林のこと、気にはなっているけど、よくわからない…」そんな方こそ、まずはご相談ください。
行政書士として、相続・登記の手続きから、
FPとして、将来に向けた資産整理まで、
あなたとご家族の山を、未来につなげるお手伝いをいたします。
▶ご相談はこちらからどうぞ
2025年7月28日
« 第3回:想いも財産も、次の世代へ確実につなげる 第5回家を建てたいけど土地が農地だった!?―農地転用のリアルな手続きと落とし穴 »