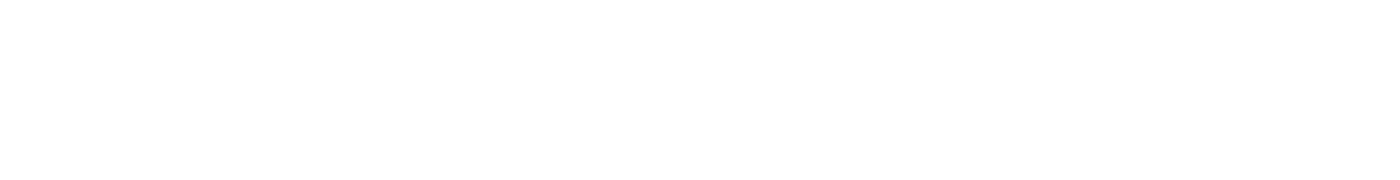第1回:相続か贈与か
第1回:相続か贈与か
~「相続」が「争続」になってしまわないよう、行政書士がお手伝いできること~
【具体例でわかる!】住宅取得資金の贈与・遺贈のポイント
「後から後悔しない『お金の渡し方』を考えましょう」
暮らしの手続きアドバイザー、FP行政書士 瀬崎です。
【きっかけとなった相談の例】
「子どもが家を建てることになって、頭金を出してあげたい。でも、これって『単なる贈与』?それとも『特例』が使える?」これは、実際によくあるお声です。
例えば…
Aさん:「長男が家を建てるから、1000万円出してあげたい。」
Bさん:「娘のマイホーム、自己資金だけじゃ難しそう。」
Cさん:「後から『贈与税』で困らせたくない…。」
こんなお悩みにお答えします!
【住宅取得等資金の贈与のポイント(チェックリスト)】
(1)贈与には、 「年間110万円までの非課税枠」がある
「住宅取得等のための贈与」であれば、最大1,000万円(省エネ・耐震性のある住宅)/500万円(その他の住宅)が非課税
(2)「受贈者(もらう側)」の年齢・所得条件がある
18歳以上/年間合計所得2,000万円以下
(3)「取得する住宅」にも条件がある
床面積が50㎡以上など(年・条件次第)
※ 「単なる現金贈与」にしてしまうと、贈与税の対象となる可能性がある
【具体例:長男が家を建てるAさんの場合】
預貯金から 1,000万円 を出してあげたい!
家が「省エネ・耐震性のある住宅」であれば、1,000万円の非課税枠が使える。そうでない住宅でも、500万円まで非課税
この特例を使わず単なる贈与なら、
(1000万-110万)= 890万円が課税対象となり、相応の贈与税が発生!
【後から後悔しないポイント】
特例を使うなら、必ず条件を確認
「単なる現金渡し」にせず、住宅取得のための贈与であることを書面で明確に
家族で「後から争わない・後から後悔しない」ため、早めの相談・準備を!
【まとめ】
単なるお金のやりとりではない、「家族の未来への投資」に
単なる贈与・遺贈だけでは後から後悔が生じることも。
「後から後悔しない」「家族が笑顔で受け取れる」、そんなカタチで進めたいものです。
もし、
「うちの場合、どんな特例が使えそう?」
「後から税務署から聞かれたくない…」
「何から手をつければよいかわからない…」
という方は、ぜひ一緒に整理してみましょう!暮らしの手続きアドバイザー、FP行政書士 瀬崎でした。
2025年6月23日