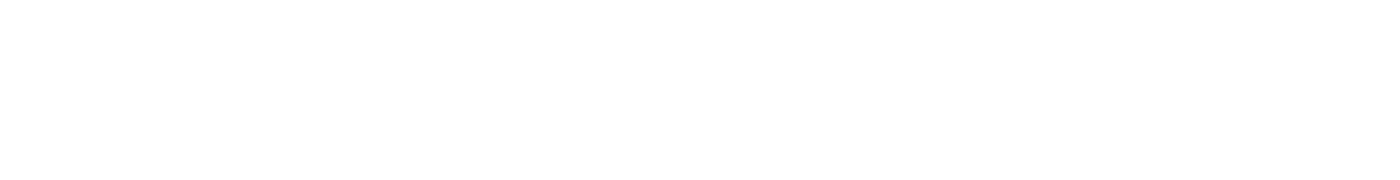第5回家を建てたいけど土地が農地だった!?―農地転用のリアルな手続きと落とし穴
「この空き地に家が建てられたらな…」
実家の田んぼ、親から譲ってもらえる畑、地方で見つけた広い土地。そんな夢の一歩手前で立ちはだかるのが――“農地”という壁です。
実は、日本の法律では農地に勝手に家を建てることはできません。今回は、そんな「農地転用」のリアルな流れと、注意すべきポイントをわかりやすくお伝えします。
農地には“建てられない”という大前提
農地とは、田んぼや畑など耕作のために使われている土地のことです。この農地は、「食料の安定供給」や「土地の保全」といった国の目的のために、農地法という法律で厳しく守られています。
ですから、たとえ自分の土地でも「家を建てたい」場合は、農地転用の許可を受ける必要があります。
農地転用の手続きはこう進む
農地転用の流れは、以下のようになります(例:市街化調整区域)。
1. 【現地調査・法的確認】
・その土地が本当に農地かどうか
・都市計画区域か、市街化区域かどうか
→ 自治体や農業委員会に確認します。
2. 【農地転用申請書の作成】
・土地の現況
・転用の目的
・添付書類(位置図、公図、案内図、建築計画など)を整えます。
3. 【農業委員会へ申請】
・毎月1回程度の締切がある自治体が多く、申請から許可まで1〜2ヶ月かかるのが一般的です。
4. 【許可後、建築申請などへ進行】
・農地から宅地等への転用が認められると、建築や造成の計画を進められるようになります。
実は多い!農地転用の“落とし穴”
農地転用でよくあるトラブル例をご紹介します。
❌ 勝手に整地してしまった
→ 無断で造成してしまうと、「無許可転用」として罰則の対象になることがあります。
❌ 自分の土地だと思っていたが、他人名義だった
→ 名義変更をしていないと、転用申請が通りません。
❌ 「畑だからOKでしょ?」という勘違い
→ 畑も農地です。田んぼと同じく転用が必要です。
❌ 隣地と一体で使っていたが、境界があいまいだった
→ 建築許可の際にトラブルの原因に。
行政書士に依頼するメリット
農地転用は法律・行政手続き・図面作成など、多くの知識と実務が必要です。行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
• 事前調査をスピーディーに
• 農業委員会との事前相談・調整
• 必要書類の収集・作成を一括でサポート
• 土地家屋調査士・建築士など他士業との連携も可能
「
農地でも、夢のマイホームは実現できる
農地転用というと「面倒そう」「自分には無理」と思う方も多いかもしれません。しかし、正しい手順を踏めば、農地にも家は建てられます。
大切なのは、「早めの確認」と「信頼できる専門家への相談」です。
🌱 ご相談はお気軽にどうぞ
農地転用や不動産活用、相続に絡んだ土地の手続きなど、お困りのことがあれば、行政書士・FPとしてサポートいたします。初回相談は無料です。ぜひ一緒に整理してみましょう!
暮らしの手続きアドバイザー、FP行政書士 瀬崎でした。
2025年8月8日
« 第4回:行政書士・FPが教える「山の未来」の守り方 第6回 【補助金・防災・従業員の安心にも】事業継続力強化計画ってなんですか? ― 行政書士・FPが支援できる、中小企業の“いざ”への備え ― »