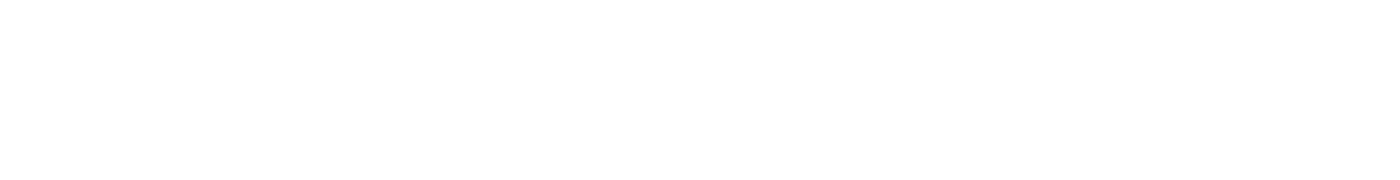第3回:想いも財産も、次の世代へ確実につなげる
「遺言、遺産分割、そして生前贈与──大切なのは『つながり』です。
遺言、遺産分割、そして生前の贈与。これらはいずれも、あなたの大切な財産や想いを次世代へ伝え、次のステップへ進めてもらうための手段です。しかし、多くの方がそれぞれ単発で考えがちです。
例えば、こんなお声をよく聞きます
「遺言を書いておけば、後の相続は大丈夫だろう。」
「遺産分割だけきっちりできれば、もめ事も起きない。」
「生前贈与で相続税対策だけしておけば十分。」
その一つ一つはもちろん大事です。でも、単発で考えたり、「後から考えればいいや」で後回しにしたりしていると、後で予期せぬトラブルや家族のすれ違いが起きることがあります。
【Point 1】遺言だけではカバーできない「後の話」
遺言があれば、亡くなった後の分配ルールが示せます。ただ、遺言だけではその背景となる「家族の想い」や「事業の後の姿」、さらには「その後の管理・運営」にまでは手が届きません。
【Point 2】遺産分割と生前贈与の『バランス』が大事
遺産分割だけで公平・公正を確保できればよいのですが、「生前贈与」を行うことで、後からの紛争を避けたり、後継者の立場を強めたりできることもあります。
ただ、単なる贈与だけでは遺留分問題など新たな火種となることも。遺言・遺産分割・生前贈与の3つを一緒に検討することで、「後から後悔しない設計」ができるのです。
■事例1:生前贈与があった兄弟間での相続争い(「争続」となってしまったケース)
Q. 父が亡くなり、遺言には「長男に自宅を相続」と書かれていましたが、次男である私は納得できません。長男は生前に父から1000万円の贈与も受けており、不公平に感じています。
A. このようなケースでは「特別受益(生前贈与)」の有無や金額、遺言の効力、遺留分(最低限の取り分)を総合的に判断します。遺言があっても、生前贈与の扱いや相続人間の公平性に配慮しないと、トラブルの原因になります。
▶ 遺言を書くときは「贈与の事実を明示する」こと。
▶ 分割協議では「受益分を反映させる設計」が重要です。
■事例2:遺言はあったが、記載内容が古くトラブルに
Q. 数年前に書かれた遺言に基づいて手続きしようとしたところ、既に処分された不動産が書かれていて話がややこしくなってしまいました。どうしたら?
A. 遺言内容が現状と合わない場合、その部分は無効とされることがあります。
このようなケースでは、定期的な遺言の見直しや、遺言とは別に「家族信託」などを活用する方法も検討されるべきです。遺言も“鮮度”が重要なのです。
【Point 3】『つながり』で後からも生きる対策へ
遺言、遺産分割、贈与を単なる「単発の対策」にせず、「次の世代へつながるストーリー」にしてみませんか?
例えば、
「遺言」で大枠を示し、
「遺産分割」で具体的配分・条件を調整、
「生前贈与」で次世代の後継者を後押しする。
その全体が『つながり』となり、家族・会社・財産の未来を豊かで安定したものへ導きます。
【まとめ】次の世代へ『安心』を設計する
単発の遺言だけ、単発の遺産分割だけ、単発の贈与だけでは十分とは言えません。これらを一緒に検討し、組み合わせ、調和した「次世代への設計」にしておくことで、後の紛争を防ぎ、家族・後継者・会社の未来へ『安心』をつなげることができます。
ぜひ一緒に整理してみましょう!(お問い合わせはこちらから。) 暮らしの手続きアドバイザー、FP行政書士 瀬崎でした。
2025年7月15日